江戸時代になると徳川家康は江戸に幕府を開いて行政の中心にしました。その江戸から十三里半に当たる川越は北から攻めてくる仮想の敵に対して江戸の街を守る拠点として位置付けています。そのため川越には譜代大名が配置されて、その多くは老中、もしくは大老格の待遇を受けていました。例えば家康の股肱の臣であった酒井重忠、知恵伊豆として知られる松平信綱、綱吉に引き立てられ御側御用人として権勢を振るった柳沢吉保などの名が上げられます。この人達は幕府の執行機関にいましたので江戸と川越の両方の行政を行うことになったわけです。江戸での政治的判断はそのまま川越の政治として反映されることが多かったと思われます。
こう言ったことも川越が小江戸という愛称を唱えていく下地になっているのかもしれません。
家康が亡くなると、生前から家康は自分を江戸城の鬼門に当たる日光に祀るようにと言い残しておりました。駿府城で没した家康は遺言により一度は久能山に埋葬されています。その後一年後に日光へ移送されるのですが、その道は御尊櫃御成道(ごそんひつおなりみち)と呼ばれています。江戸を通らない街道をわざわざ整備して久能山から三島市、湯本、町田市、相模原市を通って川越の現在の喜多院に立ち寄り、喜多院の住職で黒衣の宰相と呼ばれていた天海僧正が供養を執り行い、また日光へ移送されていきました。喜多院は徳川家光の頃に火災に遭いますが、徳川家の篤志により江戸城の建物の一部を移築して再建されました。
経済の方では、日本海側の産物が川越に運ばれ、新河岸川を使って江戸に船便で送られたり、江戸から舟便で川越へ送られ、そこから北の方へ馬や馬車を使って運ばれていきました。また近くには養蚕が盛んに行われていた秩父地方を控え、その製品の中継地でもあり、繊維工業も行われていました。この舟運は鉄道の普及が及んでくるまで続き、これによって川越に多くの富の蓄積がなされました。それが蔵造りや大正ロマンの街並みの形成へ繋がっていきます。舟運の始まりは仙波東照宮の造営の時から始まったと言われており、その後、民営での運用が始まりました。平底の船が帆を掛けて人や荷物を大量に運んでいました。江戸の船着き場は今の花川戸付近で、川越の方には仙波河岸、上新河岸、下新河岸などがあり、今も当時の船問屋の建物が残っています。
喜多院は平安時代初期(830年)に関東に天台宗を広めるために、淳和天皇の命により
無量寿寺が創建され、円仁(慈覚大師)に布教させたのが始まりです。その後起こった平将門の騒乱等により寺は衰退していきますが、鎌倉時代には伏見天皇の命により勅願寺として復興され、関東一円の天台宗の総本山の地位が与えられています。当初無量寿寺は
仏地院(現在の中院)を中心に形成
されていました。その後
仏蔵院(北院)や
多聞院 (南院) が創建されて、無量寿寺の中に三院が存在する形になりました。その
無量寿寺は後奈良天皇から
星野山(せいやさん)の扁額を賜りましたが、江戸時代になって
無量寿寺仏蔵院(北院)の住職に天海僧正が着任しますと
仏蔵院(北院)という名称を喜多院へ名前を変えています。一時期
星野山の号を東叡山(東の比叡山の意味)に換えて掲げていましたが、天海僧正が上野寛永寺に移る時に東叡山の扁額も上野に移行して、
喜多院は
星野山を再び掲げるようになります。ここで現在の
星野山無量寿寺喜多院、
星野山無量寿寺中院となるのです。(
多聞院(南院)は明治の頃、廃院になっています。)
仙波東照宮は元の中院の場所に建てられ、幕府の直轄の差配を受けるようになります。当時は神仏が同時に祀られることがありましたので、喜多院の一部分として、隣接していた中院を南の方向へ移して、中院のあった場所に新しく仙波東照宮を置いたと思われます。(明治時代の神仏分離令により、
喜多院と
仙波東照宮は完全に別な組織になりました。)
[星野山無量寿寺喜多院]
| 喜多院を訪れる時に、徳川家康、天海僧正、徳川家光、春日局を重ね合わせて考えると面白いストーリーが考えられます。二代将軍秀忠は三代将軍に家光の弟の忠長を据えたいと思っていました。しかし家光の乳母であった春日局は隠居していた家康に、秀忠の長男である家光を三代将軍になれるように訴え出ています。しかし単なる乳母が隠居していた大御所の家康に,、そう簡単に面会できる訳はないと思われ、そこに家康に絶対的な信頼を勝ち得ていた天海僧正がその間を介したのではないかと思えるのです。それは喜多院が火事で焼失した時に、天海僧正が喜多院の住職であったことから、家光誕生の間や春日局の化粧の間が移築されたという事実によって、示されてくるように思えます。 |
 |
 |
 |
| 正面入り口と前庭 |
太鼓橋になった渡り廊下と前庭 |
中庭 |
| |
|
|
 |
 |
 |
| 庫裏から書院を望む |
書院から庫裏を望む |
庭園 |
[喜多院五百羅漢像]
| 羅漢さまとは無学僧のことを言います。その場合の無学僧とは、学問を尽くされてもう学ぶことがないというお坊さん達です。既に悟りに達していらっしゃるのでしょう。羅漢さまはいろいろな表情を浮かべていらっしゃいます。この表情から面白そうな言葉を添えてみました。そうしますと益々、親しく、愛らしく見えてきます。 |
 |
 |
 |
| ”退屈だな~”、”何か言ったか?” |
”ひそひそ”、”うんうん” |
”般若湯か?”、”気すんな、長生せんぞ” |
| |
|
|
 |
 |
|
| ”あ!小泉元首相” |
”こちらは草薙君だ” |
|
[星野山無量寿量寿中院]
| 喜多院から少し南へ行った所に静かな佇まいの中に中院があります。正門をくぐると直ぐに枯山水の庭があります。枯山水は流れる川を小砂利で表しています。訪れた時、ちょうど白梅が綺麗に咲いていました。 |
 |
 |
 |
| 中院の正門 |
枯山水の庭 |
枯山水の庭 |
| |
|
|
 |
 |
|
| 本堂入り口 |
鐘撞き堂の門 |
|
[仙波東照宮]
| 日光東照宮は各地に存在していますが、日光、久能山、川越の仙波が三大東照宮に上げられています。 |
 |
 |
 |
| 拝殿 国の重要文化財 |
本殿(囲い塀越し) 国の重要文化財 |
本殿の正面側(同) 国の重要文化財 |
[仙波河岸]
| 新河岸川を使った海運事業の発展は川越に大きな富をもたらします。また当時では大量の荷物の運搬や人の移動を簡単にしました。午後四時頃川越を出た船は翌日の十二時頃には花川戸へ接岸していたと言われております。これは川越夜船と呼ばれて当時、旅のルートとして脚光を浴びていました。今は仙波河岸は仙波河岸公園として整備されています。 |
 |
 |
 |
| 仙波河岸公園 |
現在の新河岸川 |
舟問屋伊勢安(当時のまま) |
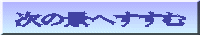
![]()





















