
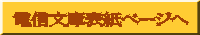

縄文時代の頃の川越
縄文時代の東京湾の海岸線を見てみますと、
東京湾が入り江(
古入間湾)となって内陸部まで広がっていました。これは氷河期が終わって、気温が高くなって世界各地の氷が溶け出して海面が上昇した事が一因ではないかと言われています。これによって海岸線が内陸部へ広がっていったと想定されています。近代になって川越の南の方にある
新河岸付近で、海に生息していた貝殻の集まった貝塚が幾つか見つかっています。また淡水系の貝殻の貝塚はもう少し北にある
小仙波付近にも存在していて、この当たりには縄文時代の竪穴式居住の跡が見つかっています。他にも縄文時代前期や中期の貝塚や縦穴式住居跡が川越の付近には、幾つも見つかっています。このことから川越付近まで海岸線が来ていたことがわかりました。この海岸線の内陸への進行は、この時代の名前を付けて
縄文海進と呼ばれています。この
縄文海進の時代の
東京湾は
古入間湾のように西に延びる部分と、北へ延びる
奥東京湾があり、
奥東京湾は群馬県や栃木県境付近まで至っていました。一方その頃の千葉では現在の
霞ヶ浦が四方に広がり、現在の千葉県付近は一部繋がっていましたが、四方海に囲まれて島のようになっていました。しかし縄文時代の後期には現在の東京湾の線に近い所まで、海は後退して行きました。
一方、この
縄文海進は気温の上昇だけが原因ではないとも言われています。それは日本以外の場所では同じ時期には、海岸線の動きが見られなかった所もあり、日本付近の地盤の変動も関与していたのではないかということが言われているようです。近年の研究では、気温の変動と地盤面の上昇や、海底面の沈降などが関連して
縄文海進の動きがあったと考えられています。この縄文後期の
縄文海進の後退によって、今まで海から貝や魚を求めて生活していた縄文人は海岸線の移動と共に居住地を移動していきました。そのため川越付近では、その後の生活跡の情報が少なくなっていきます。
 |
 |
| 縄文時代の海岸線の変化(*資料参照_1) |
川越市付近の縄文史跡(*資料参照_1) |
| 資料参照_1は川越市発行の”川越の歴史”より転載しています。 なお、縄文海進については多くの情報がありますのでWebで検索し、画像等でご覧下さい。 |
弥生時代から鎌倉期初期の川越
縄文海進の後退から広がった大地は、低湿な平地となり、そこに
荒川や
入間川、新河岸川、小畔川などの川が出来てきます。時の変遷につれてそれらの川は幾度か氾濫を起こし、塩分を含んだ土地も川によって洗浄され、また運ばれた栄養分が蓄積して肥沃な平野を創っていきます。それと同じ時期に、稲作が大陸から伝わってきて、新しく開けた関東の平野部で稲作を行うために人々が集まってきました。川越でも同じように肥沃な土地となった入間川、新河岸川、小畔川の近くの平坦地で農業が行われていきます。それは弥生時代の集落がこの地に幾つか点在することから推測されています。川の近くの肥沃な所で稲作をやっていましたが、幾度も川の氾濫に遭ったため、住処は近くの少し小高い台地の上に造られていきます。川越市の
南山田、猫田、霞ヶ関付近には当時の弥生時代の住居跡が見られています。
昭和41年頃発掘調査が行われた
霞ヶ関遺跡では46個の居住跡が見つかり、その中の一部にはかなり規模の大きな居住跡が見られたことから、すでに組織的な社会ができつつあった可能性が考えられています。最近の霞ヶ関遺跡の発掘調査では掘立柱の跡も見つかっており、入間郡の庁舎があった可能性もあると考えられています。また近くの河越館跡の発掘調査では、奈良時代から平安時代に掛けた地層から”入厨”と書かれた土器が出土しています。この”入厨”とは入間郡の備品という意味と考えられ、この付近に入間郡の役所があったのではないかと推測されています。

霞ヶ関遺跡発掘時の航空写真(*参照資料_1)
参照した資料_1は川越市発行の”川越の歴史”より転載
鎌倉期前後の川越
弥生時代から奈良時代、平安時代になって、貴族社会の中に次第に武家が台頭してきます。平治の乱の頃には秩父氏から別れた一族が入間川の近くの上戸に居住地を構えて河越氏を名乗っています。この場所は入間川が南から北へ、そして東へ、今度は北から南へと大きく湾曲して流れており、川が自然の堀となって守りやすい地形となっています。河越という地名もこういった地形から名付けられたものと思われ、秩父氏の別れた族がこの地に居を構えた時に、この付近の地名として通っていた河越を氏名にしたと考えられます。この頃、川越の地名は河越や河肥の文字が当てられていました。現在の川越という文字が使われるようになったのは、江戸時代のはじめ頃になってからだと考えられています。秩父氏は桓武平氏の系統であったため、河越氏も平氏に属していました。しかし源頼朝の蜂起の後から源頼朝の下につき活動して行きます。また当時の当主であった川越重頼は娘の郷御前を義経に嫁がせて確固とした地位を築きますが、義経と深く結びついた事から、頼朝と義経の間の争いが起こると幕府から遠ざけられていきます。北条氏の政権では少し復活しますが、その後起こった平一揆で敗北して滅亡の道を進んでいきます。
現在この河越館跡は発掘調査が終わり、保存のため埋め戻されて、川越館跡公園として公開されています。
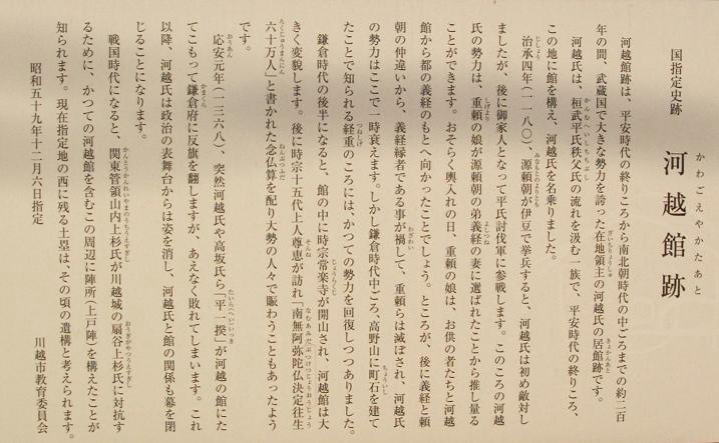 公園入り口の説明看板
公園入り口の説明看板
 |
 |
| 発掘調査の状況 撮影2008年 |
文化財指定表示 |
上記写真は、2008年頃行われていた発掘調査の様子です。左側の写真は現在の河越館跡史跡公園になっている所で、右側の写真の土を盛った向こう側の部分になります。また右側写真の部分は2021年の頃、発掘調査が行われています。この2008年の発掘調査で、この場所が河越氏の館跡と断定されましたが、河越氏の館本体は、左写真の左側にある小学校敷地内にある様で、現在その場所の発掘調査までは至っておりません。しかし史跡公園内では、使われていた井戸や小屋の建物跡、掘り割り、本棟の隅部分の基礎跡と見られる部分などが見つかっています。
鎌倉期から江戸期前の川越
河越氏の支配が崩れ去った後は、縄張り争いの場所となって行きます。上杉、北条、足利公方などお互い自分の陣地にするために激しく争い、戦場の場になっていきます。そして豊臣秀吉の登場で、前田利家の支配下になり
その後、徳川家康の支配する区域として組み入れられていきます。
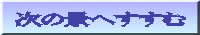
![]()



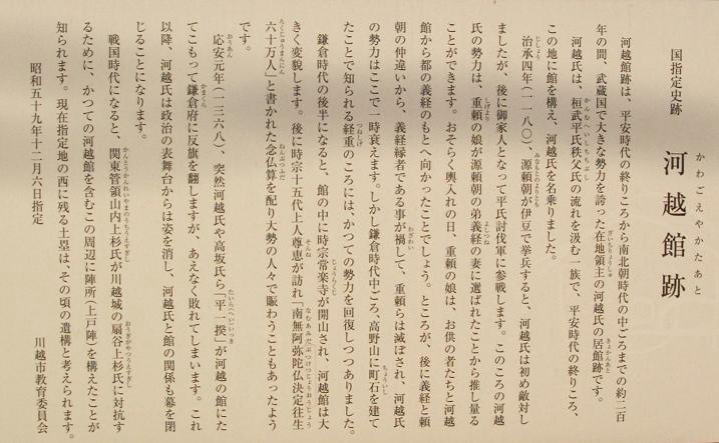 公園入り口の説明看板
公園入り口の説明看板
