

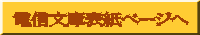
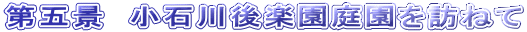 (2012年10月6日 訪問)
(2012年10月6日 訪問)
後楽園といえば、ドームの野球場を思いつく人が多いかもしれません。元々は江戸時代初期に、水戸藩の藩邸が小石川に設けられた時に、その中に回遊式庭園が造られました。回遊式庭園が完成したときの藩主であった光圀公が明の遺臣の意見を元に”後楽園”と名付けたと言われています。後楽とは”人の楽しみを後れて楽しむ”という意味です。この場合の人とは、庶民のことを言います。つまり”君主は庶民が楽しんだ後に楽しむものである”という政治家の姿勢を言ったものです。どこかの国の政治家に教えてあげたい言葉ですね。しかしこれについては黄門様にお伺いしなければなりません。後楽園庭園は、庶民でも楽しむことが出来たのでしょうかと。少し難しい様な気がします。しかしいまは深く触れないでおきましょう。
ドーム球場の裏手に当たる場所に、小石川後楽園があります。後楽園の地下鉄の駅からドーム球場の方へ行き、グルーッと回った南西角に入り口があります。門から少し中へ入ったところに、事務所がありました。お金を払い、券を貰って振り返ると、キンカンが置いてありました。あのかゆみ止めの薬です。さすが気が付く。しかしここでは日がたっぷり当たっているので蚊は出ません。庭園の奥の木の鬱蒼とした場所に沢山出るのでしょう。そこで刺されて、ここまで戻って来るのは大変だな~と思いながら中へ入っていきました。入るとすぐ左手に、芝に覆われたなだらかな稜線の双子の山が見えました。まん丸い月が似合いそうです。その脇を通り、進みますと土橋の掛かった池があり、向こう岸には枯れ滝の様な石組みが見えます。また池の左手には西湖堤がありますが、その存在感は視点が逸れる為、あまり強くありません。土橋を渡って岩の近くに立つ案内板を見ますと”屏風岩”とありました。しかし岩をよく見ますと、水がしたたり落ちる様な斑が見られますので、多分、枯れ滝の磐組として造ったものと思われます。その滝組の所から池までは玉石の滝壷が造られ、その玉石の流れが池の方へ続いています。そして向こう岸には滝のようなものもみえます。歩いていて感じたのですが、ここの庭園全体の歩く道や階段に、石が敷かれており、そのパターンの多様性を楽しみながら歩くことができます。その膨大な石の量は、何故そこまでする必要があるのかと思わせるものです。園内の地盤面の高低差は大きく取られていて、登ったり降りたりして、景観の多様な変化を味わえるのです。そして造られた山のゾーン、谷のゾーンのポイント、ポイントには朱塗りの木造の橋である通天橋や、石造りの半円の形を取った円月橋など、目を楽しませる変化もゾーン毎に造られており、回遊式庭園の面白味を高めている様に感じました。また今はそれぞれの花の時期ではありませんので観ることは出来ませんが、園内には花畑がいくつかあり、いろいろな花も楽しめそうです。私が訪れたときは、彼岸花が沢山咲いていました。少し時期が過ぎた頃で、あの激しい色や形も崩れ始めている様でした。春は水戸に関わりの深い梅、そして枝垂れ桜など、初夏には花菖蒲や杜若やツツジなど、夏には睡蓮、秋には紅葉が楽しめるようです。通天橋近くの谷間から、先ほど渡った土橋の写真を撮ろうとカメラを構えたとたん、アベックが橋を渡り始め、そして真ん中で立ち止まってしまいました。そこから池の鯉に餌をやったりしている様です。十分ほど待ちましたが立ち去る様子を見せません。私の周りには数匹の蚊が飛んでいて、あちこち刺されてしまいました。先ほど見たキンカンが頭にちらついてきます。しょうが無い。あきらめて大泉水と呼ばれている池の方へ進むことにしました。池の開けた先に高層ビルが見え、池にその姿を写しています。
少し池の周りを歩いて山へ入る。先ほど述べた石の円月橋を観て、その脇から丘に登りました。丘の上には八卦堂跡の展望台があり、そこから水盤越しに穏やかな景色が眺められます。その風景の中には、彼岸花が紅色を添えてくれています。石段を降り、梅林を過ぎると丸石を段先に並べた緩やかな段々の向こうに、九八屋という建物が見えました。さらにもう少し進むと、先ほどの大泉水の反対側へ出ます。沖の蓬莱島に擬された島の岸の岩に、紅葉した紅葉が色を添えていいます。
 |
 |
 |
| 高層ビルも景観を引き立てる |
八卦堂跡の展望台から |
階段先の九八屋 |
| |
|
|
 |
 |
|
| 湖畔から蓬莱島を見る |
蓬莱島の紅葉 |
|
その左手、敷地全体の東南の角に、少し脇道に逸れる部分があります。図面で見ると、敷地が付け足された様な部分になっています。今まで紹介した庭は、表の庭として造られた部分ですが、この付け足された様な部分は、表庭の1/8程の大きさの内庭として書院から観られる様になっていたらしいのです。昔は表庭と内庭の間には門があって仕切られていたそうです。今は二つの庭は一体として見学の対象とされています。しかしよく観ると庭の構成が異なっていることが分かります。この内庭には確かに落ち着いた雰囲気があります。表庭が視点の多様な変化を楽しむところであれば、内庭は自然の造る奥行きの変容を楽しむところとなっている様に思います。私にはこの内庭の醸し出す自然の存在が、快く感じました。
 |
 |
| 内庭の白壁と笹の植え込み |
内庭の池に掛かる石板の橋 |
この内庭を一周してまた大泉水の湖畔へ戻り、出口の方へ進みますと、渓流を模した川があり、一枚岩の橋が掛けられている所がありました。右手には大泉水がありますので、そちらに目が行っていますと見逃す位置にあります。一枚の岩の橋と川辺の造り、周りの木々が一景を造っています。その右手には楓の老木が立っていて、昔枝を切られた跡に別の植物が共生している姿が見られました。名前は分かりません。それも自然の営みなのだと思いながら、小石川後楽園をあとにしました。
 |
 |
| 静かなる風景 |
自然の共生 |
いろいろなパターンの石畳があり、それらを見比べながら歩くのも楽しい。





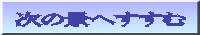


![]() (2012年10月6日 訪問)
(2012年10月6日 訪問)












