

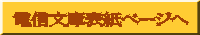
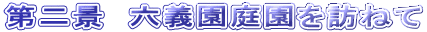 (2012年8月26日 訪問)
(2012年8月26日 訪問)
旧古河庭園と六義園は、駒込駅から歩いて行ける距離にあります。駒込駅の北にある旧古河庭園を先に訪れ、そこから南の方向へ歩いて、六義園に向かいます。その途中の駒込駅から旧古河庭園までは、下町のような町屋が並んでいましたが、駒込駅付近から六義園の方に掛けては、新しいビルが建ち並ぶ街並みへ突然に変化ています。この変わり様は何だろうと思いました。山手線の内外でこんなに違うものでしょうか。実に面白い状況だと思います。駒込駅を通り過ぎ、南へ少し歩きますと六義園の入り口が見えてきます。しかしそこが入り口ではありません。近づいてみると大通りの方を示す矢印があって、入り口はこちらとなっています。大通り側に入り口があるのかと思いきや、そうではありません。そこからまた大通りを南に同じような距離を歩かされて角を曲がった所にやっと入り口がありました。何で駅から最も近い所が入り口になっていないのだろうかと思います。駅に近い最初の門は染井門と名付けられていましたが、江戸城からは反対になりますのでこの染井門は裏口になったのでしょうか。大通りから脇道に入ったところに煉瓦造りの塀があって、その先に門があり、正式な入り口になっています。煉瓦造りの門を入ると右側に券売所がありましたが、その建物はプレハブでした。煉瓦の門には実に不釣り合いな様な気がしました。パンフレッドをみますと左手に管理事務所とありましたが、現場ではそこの部分に簾が立て掛けられています。どうやら何んらかの工事が行われている様でした。つまり券売所は仮設なのだろうと思われ、それで納得しました。入るとすぐに道は二つに分かれています。私の前に入られた二組の連れは右に行かれましたが、天の邪鬼の私は左手に行くことにします。(決して根が天邪鬼なのではなく、写真撮影の時、その人達が撮影の障害になる可能性が高いからで、今までの経験からの行動です。)左手に少し行くと木造の門がありました。その所に書いてあった案内板によると、後で造られた門(内庭大門)のようです。ここからが庭へ入る本当の入り口になるのです。しかしすぐ左手には細い竹で造られた門がまたあって、そのあたりの意味がよく分かりませんでした。庭に門を付けるという事も疑問なのです。門は外と内を区切るもので、庭は自然の中に繋がりがあって意味あると思うのです。つまり門の存在することで、ここで庭を区切ると言う意味になり、自然な庭への導入の障害になると言えると思います。竹の門を入ると、広大な庭が突然に目に入ってきました。広々とした池の周りに、また広々とした芝生の庭が広がっています。なるほど。六義園の造成には柳沢吉保も設計に参画したとも伝えられています。この庭園は当時の大名屋敷の中に造られた回遊式池泉庭園であり、同じ回遊式池泉庭園でも京都などの寺院にある庭園とは趣が大きく異なっているようです。何せ規模が大きい。ついつい柳沢吉保の権力者としての政治力を、垣間見た思いがしました。そこかしこに千両箱が積み重ねられ、池や山が造られたという幻想すら起きてくるような雰囲気になります。この景観に私のような貧乏人は、少し身を引いてしまう気分になってしまいました。
 |
 |
 |
| 六義園 田鶴橋を見る(中央奥) |
六義園 中之島を見る |
六義園 心字池 |
| |
|
|
 |
 |
|
| 六義園 臥竜石 |
六義園 雪見灯籠 |
|
確かに権力者として将軍を迎え入れて催される園遊会などでは、諸大名、公家、旗本など多くの人達がこの庭を眺めにやって来るでしょうから、その人数に負けない庭を造るとなればこうなるのかもしれません。そういった想像の中には柳沢吉保の得意絶頂の高揚した顔が見えてくるようです。先に進みましょう。右手には雪見灯籠がありますが、ただ一基だけ、ぽつねんとした佇まいで立っています。雪見灯籠を中心に奥に池と小島の緑を配置し、手元には刈り込みがされた低木、そして右手には動きを感じさせる松を配しています。それぞれが遠近にあるので撮影ポイントを選んで撮影できます。左手の南側には心泉亭、宣春亭という茶室もあります。池を巡る道を歩いて行くと池の中に岩が組み合わされて、観覧者の視点を集めものが置かれています。それには臥龍石という名前が付けられていて、あたかも龍が池の中から、その姿を見せているような形をしています。その先には木が生い茂る小島があり、一つの絵を造っていると言えるでしょう。この場所が作庭者の一番のおすすめポイントとなるのでしょうか。素人の私には少しやり過ぎの自慢話のように見えます。さらに足を先に進めると橋があり、左手には滝見茶屋と書かれた案内板があって、その奥に東屋が見えてきます。しかしその周りの水は白く濁っていて、滝の様子などはうかがえないので遠くから眺めるだけにしましょう。そこから先は二股になっていて森の中を進む山の道と、池に沿った海の道とに分かれています。海の道は先ほどから見ていたので、新しい発見を求めて山の道へ入っていきます。ツツジや紅葉の頃にはきっと見応えのある木々もある様ですが、今は特段に心が引かれる物はありません。ツツジの茶屋と書かれた所をを通っていきます。パンフレッドによればツツジの古木で造られているようです。建物の柱や梁材を採れるだけの大きさのツツジがあるのだと、感心して眺めました。そこから川沿いに進み、白鴎橋を渡り、川の反対を進んでいきます。途中にある山陰橋を観て、藤波橋を渡り千里場へ出て、右に入ると出汐湊の近くに出てきました。こう言った庭園では、地方の有名な場所を模して造り、その場所の名前を付ける例が多く見られますので、名前から雰囲気を楽しむのも良いのではないでしょうか。但し、イメージが現物とはかけ離れている場合もありますので注意が必要です。
 |
 |
 |
| 六義園 山の道から_1 |
六義園 山の道から_2 |
六義園 山陰橋 |
ここの出汐湊からの眺めは良いですね。ちょうど西日が池に反射して輝いています。そこから田鶴橋も見えます。のどかな風景を前に休憩所には多くの人たちが縁台に座り、遠くに広がる風景を眺めています。少しほっとしてのんびりとした気分になって来ました。休息を取りながらパンフレッドを眺めてみます。まず私だったらどう構成するのか考えると、多分駒込駅に最も近い門から入って、少し広々とした森の中の道を歩いてもらい、その間に都会の街の雰囲気から脱出して、自然に慣れて貰ったあと、大きく開けた景観を一気に見せる方法を取っても面白いと思いました。そして開けた風景が望める解放された茶席で濃茶を一服して貰い、静けさに浸る様にしたいと思う。しかし柳沢吉保は尊崇する将軍の居城である江戸城に近い方に入り口を設けたいだろうから、現在の入り口が使用されていたのではないだろうかと思う。また大勢が入庭する場合には、最も印象深い所のみを見せて追い返したかもしれない。その場合でも現在の入り口の方が都合が良いのかもしれない。その最も印象深い部分のみを見せることで、観た人のイメージを敷地全体に広げさせれば、参観者の驚嘆を大きくする事ができるでしょう。そこまで柳沢吉保が考えたかどうか。案外そうかもしれないと思いながら、出口へと向かいました。先ほどの門の近くに行くと大きな木がありました。それは枝垂れ桜の巨木で、この巨木に花が咲けば、これも参観者を”あっ”と驚かせる装置になるのかなと思います。きっと将軍を迎えたのは、この枝垂れ桜が満開の頃でななかったかと思います。さすが柳沢吉保と感心しながら帰途につきました。

六義園 中之島に渡る田鶴橋
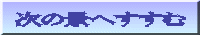


![]() (2012年8月26日 訪問)
(2012年8月26日 訪問)







