

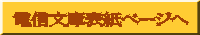
 (2012年8月26日 訪問)
(2012年8月26日 訪問)
2011年10月に訪れた京都の庭園探訪で植治七代目小川治兵衛の作品で、山県有朋の別邸である無鄰菴(むりんあん)を見て、川の流れの表現、庭園路の作り、石の使い方、借景の取り入れ方など、その手法に大変感銘を受けました。そして機会があれば、その七代目小川治兵衛が手がけた他の庭園も見てみたいと思って探してみますと、その作庭が東京にもあるということが分りました。それが旧古河庭園です。七代目小川治兵衛が係わったと思われる京都にある他の作庭についても紹介の写真は実に少ないのです。また私の捉え方とは違った写真しか見られないものも多く、不満が多く残りました。もしそのWebに掲載されている写真がベストなのであれば、七代目小川治兵衛の作品に無鄰菴ほどの期待が寄せられないのではないかという不安さえ感じさせました。そこで次回、京都を訪れる前に東京にある旧古河庭園を訪れ、その作風を探っておこうと考えました。旧古河庭園のホームページを見ますと、石造りの洋館と西洋風の写真がトップを飾り、七代目小川治兵衛が手を入れたと言われている和風の庭園の写真が一枚もそのホームページには掲載されておらず、ますます心配になってきました。
 |
 |
 |
| 旧古賀邸 正面アプローチ |
旧古賀邸 庭側から見る |
旧古賀邸 配置案内図 |
家で早めの昼ご飯を食べて電車に乗りました。私の家から歩きを入れても1時間20分位で旧古賀庭園に着くようです。入り口の受付で入園料を納めて入場しますと、左手に案内の看板があり、全体の説明と配置案内図があました。説明と案内図の大まかな所を把握して中に入ります。まずHPの中で一番の売りでありました洋館を見てみましょう。正面玄関を通り過ぎて奥側から玄関を見て、その後東側に回って洋館と花壇のコラボの写真を撮影しました。そこから洋風庭園が望める展望台に行ってみると、小学生の男の子が数人いて何かをやっているようです。静かに彼らに近づいていきますと、どうやら写生会が行われているようでした。ここの敷地は北側が高く、南側に下がっていく地形になっています。結構、高低差があって北側の最も高いところに洋館が建ち、中段に西洋風庭園が造られていて、そして最も広くて低い部分に和風の庭園が造られています。パンフレッドには洋館と洋風の庭の部分がイギリスのジョサイア・コンドルの作であると書かれていました。そして最下部に広がる和風庭園が植治の七代目小川治兵衛の作と思われます。案内板や入場券には”植治”という会社の名前が入っていました。七代目小川治兵衛の名前は記載されていないのですが、”植治”の名が入っていれば実質的には関与したと考えて良いでしょう。そのあたりは作品の内容から見て微妙な感じも致しました。私は和風庭園の方に興味がそそられていますので、洋風庭園は素通りして、すぐに展望台脇から下へ降りて和風庭園の方へ行くことにしました。和風庭園の入り口付近は森の中の道として作られており、熱い日差しを遮り、暑さを和らげてくれて歩いていても大変気持ち良く感じます。降りきった所からは分かれ道になっています。左回りでグルーッと一回りしてみました。すぐに土の橋が見えてきます。土橋の右手は心字池になっていて、橋の下を通って左側に川となって続いています。その先に滝のようなものが造られていましたが水量が少なく、その滝壺にちょろちょろと流れ出ている程度で、滝とはちょっと言い難い程のものでした。また水が落ちたところでも水量が少ないため、流れが作れなくて白い淀みになっています。その淀みはドブ川を連想させて決して美しくは見えません。名匠と言われている小川治兵衛が見たら、何と言うだろうと思います。この庭園では全体的に生きた水が少なく、淀みや枯渇した川になっていて、作庭当時の様子を推察することが大変難しい状態になっていました。川や滝を表現する景観に水が無いというのはある意味では致命的ではないかとも感じました。
 |
 |
 |
| 旧古賀邸 土橋 |
旧古賀邸 滝(水が少な過ぎる) |
旧古賀邸 茶室と庭(川の痕跡?) |
橋を渡った先には”崩れ積みの石垣”と書かれた看板があります。崩れ積みとは面白い表現ですが、崩れる様な石垣では石垣にはなりませんので崩れるように見えても崩れない積み方、つまりより自然に石が積み重なった積み方なのでしょう。紹介のパネルには七代目小川治兵衛の自信作だと書かれていましたが、小川治兵衛にとって、もっと他の所での評価が欲しかったのではないかと感じられました。その裏側を通る登る坂道があります。坂道は石垣によって目隠しされている様にも見えますが、その先には何があるのだろうという興味を起こさせる様に作られている様に思われるのですが、造りが途中半端なような気がしました。その道の先に茶室が見えてきました。今は使われていないようで、雨戸が立って内部の様子も見る事ができません。また茶室の庭も綺麗に手が入れられている様には思えません。茶室の庭と思われる部分には、この道と並行して川筋のようなものが造られており、もしかしたら、茶室から渓流が望めるようになっていたのかも知れません。今は枯れた窪みが長く横たわっているだけにしか見えないのです。この川のような窪みの部分の、茶室とは反対側に石灯籠があって茶室から見る一つの風景を作っていたのではないかと想像されます。”崩れ積みの石垣”まで戻り、心字池を迂回する道を進んでいきますと、川の風景に出会いましたが、その川には肝心の水がなく、その今枯れている川には渓流が形作られていたと思われる石が川中に配置されてはいて、水がないため石の存在が浮いてしまっています。もちろん、そこで表現されているはずの自然の川の様子も見られないのです。そこには川として造られているが川を表現しきれない”もどかしさ”を見る側に感じさせてしまいました。残念なことです。そこから心字池の方へ行くと玉石で造られた湖岸があり、そこには雪見灯籠が置かれています。玉石で造られた湖岸の延長を見ていきますと左手に続いていて、そこは枯れ滝の風景が作られていました。枯れ滝の風景の左手には水の流れを思わせる筋の入った巨石が置かれ、滝に見立てられています。しかしその一連の風景の中では浮いた感じになっていました。その風景の右手の少し高くなった所には、石造りの十三重の塔が見え、枯れ滝とそれぞれが主張し対立してい様に見えます。多分枯れ滝と塔の間に緑の木々を介するようにすれば、枯れ滝をメインにした風景として,十三十の塔を背景に一つの景として感じられるのではないかと思われました。
 |
 |
| 旧古賀邸 渓流のはず? |
旧古賀邸 枯れ滝と玉石の川 |
| |
|
 |
 |
| 旧古賀邸 心字池と灯籠(左手) |
同 左 |
今度は池に沿って進んで行きますと、池へ流れ込む川があり、そこに大きな一枚岩の橋が掛かっていました。その付近は結構まとまっていて少し景観の質が上がったように感じさせました。それでも”さすが七代目治兵衛”と唸らせるものが感じられないのが残念です。。先ほど近くで見た雪見灯籠を心字池の対岸から眺めて見ますと、右手のマキ(槙)の小枝を介して作られる景観が、この古河庭園の一番の見所なのかも知れないと思いました。しかしそこも少し物足りない様に思われ、無隣庵で小川治兵衛の造った三つの要素である川の表現、借景、樹木の造る内包性がここでは一つも感じられないという不満が残っています。東京という大都会の中では借景を期待するのは無理だとは思いますが、水の少なさが川や池の表現を殺していた事実があり、ここで七代目の治兵衛の作風を評価するのは出来ないのでのではないかと思われました。今度、京都の平安神宮の庭園で再度、治兵衛の作品を見て見たいと思います。
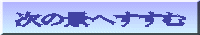


![]() (2012年8月26日 訪問)
(2012年8月26日 訪問)








