

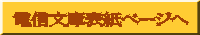
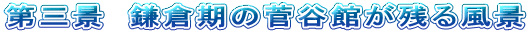
鎌倉時代の人、畠山重忠という武将が居住した館跡が埼玉県武蔵嵐山にあります。畠山重忠は源頼朝を助けて鎌倉幕府の基礎を築いた重鎮の一人です。源頼朝が鎌倉で旗揚げした時は平氏の旗を掲げて頼朝追討の側に立ったのですが、鎌倉の三浦一族に支えられた頼朝が敗れて安房の国へ渡り、そこで再起して安房の軍勢を引き連れて来た時には、他の平氏側にいた河越氏、江戸氏と共に頼朝の軍に参加しています。またその頃から畠山重忠の活躍が始まります。頼朝の弟の範頼、義経に従い、京都を占拠した義仲軍を追討し、平家を追って山陽道を攻め下り、屋島の戦い、壇ノ浦の戦いで平家が滅びるまで先陣を切って戦っています。大力の持ち主であった重忠には、おもしろいエピソードがあります。壇ノ浦の合戦の前に一ノ谷の戦いというのがありました。京都を木曾義仲に攻め取られた平氏は、平氏の経済拠点であった福原(現神戸市内)において正面は海、背面は山地という地形を得て勢力の挽回を計るのですが、義経率いる軍勢に有名な”鵯越(ヒヨドリゴエ)の逆落とし”という崖を攻め下るという思いも依らない攻撃を受けて敗退してしまいます。この鵯越の逆落としの場面で、馬が崖で足を踏み外して怪我をするのは可哀想だと思い、重忠は馬を背負って崖を下ったという話が「平家物語」に記載されています。その事実が有ったかどうかは兎も角として、その畠山重忠は板東武者の鏡として評価されています。その重忠も頼朝亡き後、北条氏により謀反の疑いを掛けられ謀殺されてしまいます。
東武東上線の武蔵嵐山駅で降りて菅谷館跡の目的地に向かいます。駅から歩いて15分ほどの所にあります。その道の途中には道しるべが立っていて、私が歩いていこうとする方向に、”蝶の里”があると書かれています。そして歩いている歩道には、オオムラサキの蝶が描かれた陶板2種類が交互に埋め込まれています。後で見た総合案内板には、菅谷館の場所の西側に”蝶の里”の名称が付けられた場所がありました。蝶の舞うシーズンにはオオムラサキ特有の紫色をした蝶が舞う姿が見られるのでしょう。しかし今回は史跡を尋ねるのが目的ですので、そこは目的地には含まれていません。しばらく歩くと菅谷小、中学校が固まった一角があって、運動会が開かれていました。小学校の父兄と思われる方達が、校門近でノンビリと井戸端会議を開いています。その学校の前の道を抜けると大きい幹線道路に出ます。その反対側が今日の目的地です。交差点にある高架歩道橋を渡り、交差点から45度の角度で茶畑の間の道を少し登り気味に入っていくと、少し開けたところにでます。
 |
 |
 |
| 国蝶 オオムラサキの歩道タイル |
大きい幹線道路から入る道 |
第3の郭(くるわ)跡 |
その付近は3の郭(くるわ)と呼ばれるゾーンです。そのまわりにはニガナ、ヘビイチゴ、アザミなどの花が見られました。左手には歴史資料博物館があり、その入り口には菅谷館跡の案内看板がありました。そこで全体配置を掴もうとしましたが、なかなかわかりにくい地図です。その案内板に、水色で描かれた堀の水たまりのような部分が有ったので行ってみると、それらしい水たまりがあります。長さ100m程、巾2m程でしょうか。堀として見れば、堀と思えます。しかし知らずに見れば、単なる水たまりにしか見えないでしょう。そこを道成りに曲がって行くと右手に小高い塚のようなものがあって、その下に畠山重忠の像と書かれた標柱と、塚を指す矢印が画いて有りました。
その当たりで何か催し物が行われています。どうやら畠山重忠公を偲ぶ会が開かれている所に来合わせたようです。いま丁度その像の前で慰霊祭が終わったところの様です。塚から少し離れたところにステージが作られ、もうすぐ歌舞音曲の催し物が開かれるようです。マイクを通したにぎやかな音がスピーカーから流れています。重忠公には申し訳ありませんでしたが、反対側へそくさくと降りていきました。少しはその塚が雑音を消してくれるでしょう。畠山重忠の像は、この当たりが彼の城館跡だと想定されてから建てられたものだと思われます。碑文が彫り込まれた石版が幾つも立っていて余り読む気になりません。畠山重忠は42歳で亡くなりましたが、像のお顔は50歳位のように見えました。塚から降りた所は、本郭の北側になります。その部分と本郭の間には深い空堀があり、2,3mほど下って、5,6m程登る様な高低差が造られています。少し西の方に回り込むと大きな梅の木が数本あり、この郭では目立つ存在です。昔は桜より梅が多く愛好されたと聞いていますが、鎌倉時代はどうだったのでしょうか。本郭の空堀に沿って南側へ回り込むと、30cm程の高さの段々が下の方へ続いています。階段は南の方向へ向かって降りています。つまりこの菅谷館は北側の高台に本館があり、建物の南は遠くを見通し出来る敷地に立っていたと言う事になるのでしょう。
急激な段差の階段を下りると少し平坦な場所になります。案内の看板があり”南郭(くるわ)と画いてありました。その案内板には南郭がどのような目的で使用されていたのかは、判っていないと書かれていました。その看板の所から左に入って回り込むと、今度は降りたのと同じくらい登っていく道になります。笹と灌木の林の中の道です。暫く登りますと本郭と思われる広々とした平坦部に出ました。100m×50m程の長円形をしているでしょうか。この部分は周囲が3~4m程の盛り土で囲まれています。
 |
 |
| 水をたたえた堀 |
本郭と周囲の土塁 |
ここに立っていると当時の城塞であり、侍大将の住む館の生活が見えるような気がしてくるのですから不思議です。北側と南側に盛り土に切れ目があってそこだけが人の出入りが許されていたのでしょう。本郭をグルーッと回った後、再び先ほど上ってきた道を下り、南郭の看板まで戻り、そこからさらに南の方へ降りていくと、ちょろちょろと水が流れている場所に短い木橋かけられています。このあたりは少し湿潤な地形にあるようです。その橋のところから木くずを敷き詰めた路になっていて、スポンジの上を歩いているような柔らかい反発が靴底に返ってくるのがわかります。右手にバンガローのような小屋が見えてきて、その前に見事な白い花がたくさん咲いているのが見えました。帰宅した後調べてみました。更紗宇木(サラサウツギ)のようです。奥のほうにも何本か満開を迎えていました。白い花が見事に咲いています。この場所は先回来た時に素晴らしいダイコンの花で埋まっていて、周囲の木立と調和した素晴らしい風景写真を撮ったところでした。しかし先日、パソコンの不調があってデータを紛失して残念に思っていました。これで取り返せたのかなと思います。道を戻り、先ほどのバンガローの所から逆の左側には、日光の湿原のように渡り道となる様に巾1mほど木材が並べられて道が造られています。夏には蛍が沢山見られる場所と書いてあります。ちょっとその先がどうなっているか気になって入ってみました。そうしますとその木道の脇に珍しい花を見つけました。これも後で調べてみました。セリバヒエンソウの花のようです。方々に咲いています。その姿は鳥が尾っぽをピーンと立てて飛んでいる様に見えることから名付けられたそうです。
 |
 |
 |
| サラシナウツギ(更科空木) |
セリバヒエンソウ(芹葉飛燕草) |
クサフジ(草藤) |
その近くにも立て看板があります。それには”まむしに注意”と書いてあります。春先の寝恍けたマムシにお会いするのは本意ではありません。すぐに木道を降りて先ほどの道を南の方へ行きます。そうすると川に沿った道路に出ました。川は都幾川で川を渡る橋の上流側では、流れてくる2つの川が合流する場所が見られました。二つに分かれた南側の川辺には桜の木が植えられていています。橋を渡って土手上の道を東へ歩いていきます。桜の木が植えられていて多分ここも桜が咲き誇る頃には、人々で埋め尽くされたのでしょう。川辺の方には紫爪草や草藤が、右手の道路側の土手には同じく紫爪草と庭石菖が咲いています。ところでなぜこの道を辿っているのかと言いますと、鎌倉街道の通ったと思われる場所をみたいと思ったからです。埼玉で鎌倉街道?と、疑問に思われるかも知れません。鎌倉街道とは鎌倉に幕府が開かれ、鎌倉と各地方との連絡を取る重要な道路が、幾つも造られました。その道路跡と思われる遺構が各所で見つかり、それらを纏めて鎌倉街道と呼んでいるのです。当然鎌倉幕府の要人であった畠山重忠の館は、その街道との結びつきが有ったと考えられ、菅谷館跡の近くを通っているはずです。もちろん町中ではそれらしいものは見ることは出来ませんが、郊外の山間いの部分を通っていたと考えられ、ルートの一端が想定できるのではないかと思われます。勿論インターネットで大凡の鎌倉街道のルートを調べ、現在の地図と合わせ、概略の位置を地図の上で割り出して来ました。そのポイントを目指して、今歩いているのです。先ほど渡った橋の下流側の橋の袂あたりが、その鎌倉街道の通っていたと思われるポイントになります。次の橋が見えて来る頃、右手の田んぼが黄土色に染められたように見えました。次第に近づいていくと小麦の穂が実りの時期を迎えています。目的の橋の袂に着いて周囲を見回しますと、橋を通って南の方へ行く道路が少し下り気味になって曲がりくねって、山間いの中に消えていっています。多分ここがそのポイントではないかと思わせるのに十分な地形です。「なるほどここを通っていたのか。」と納得。鎌倉武士が乗った早馬がこの辺りを駆け抜ける様子を心に描いてみました。この散策がさらに有意になったような気がしてきます。そして駅の方へ戻る道となる橋を渡りながら遠くを見ると、雄大な自然の中を穏やかに流れる都幾川の様子が、心の中にゆったりとした気分を醸し出してくれました。
 |
 |
 |
| 金色をした麦畑 |
鎌倉街道の路か? |
ゆったりと流れる都幾川 |
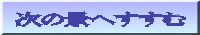


![]()
















